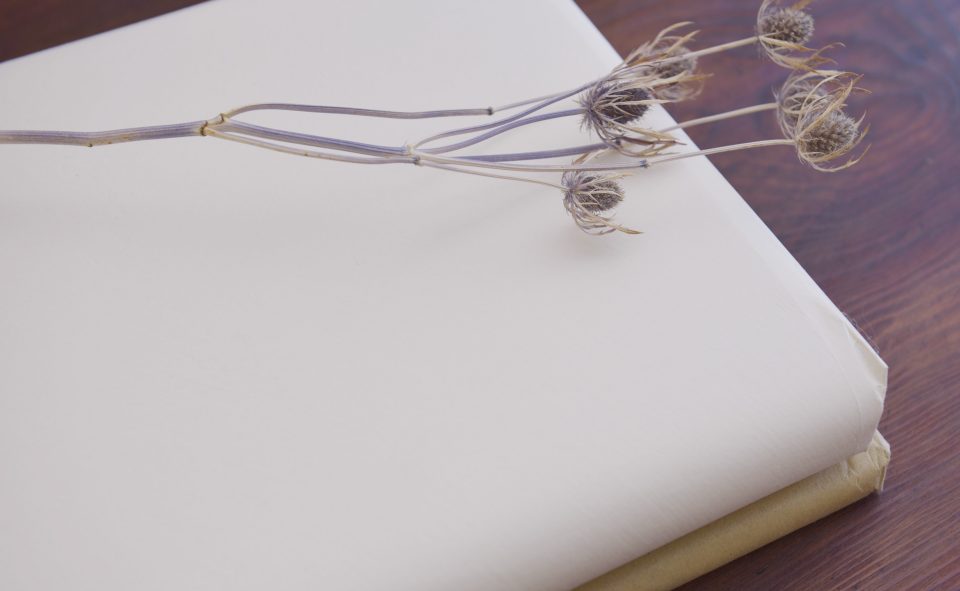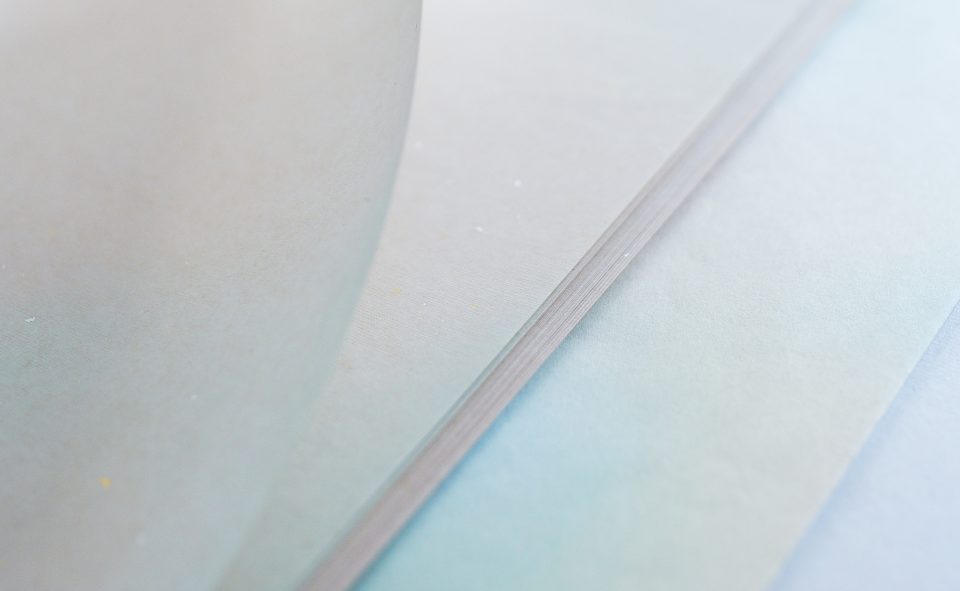書道紙は文房四宝の中でも非常に大切な役割を果たす道具です。
紙の厚さ、製法の違いにより多種多様な味わいを見せてくれます。
書道紙の保存には万全の注意を払い、より良い作品づくりに活かしたいところです。
正しい保存方法とは?
書道紙の保存は、特に直射日光と湿気に注意が必要です。
おすすめの保存場所
直射日光が当たらず、風通しが良く、湿気が少ない場所をお選びください。
桐ダンスの中、タンスの上などが良いとされています。

おすすめの保存方法
新聞紙や和紙で包むと、紙が呼吸しやすく、また直射日光から守ることができます。
書道紙の下にすのこを置いて通気性をよくしたり、湿気対策として、吸湿剤や乾燥剤を利用するのも効果的です。
また、防虫香(衣類用の防虫剤で構いません)を添えることで、虫食いの予防になります。
ビニール素材などで密封されますと、紙が呼吸できなくなるため、シミなどの原因となりますのでご注意ください。
紙を「寝かせる」とは?
「紙を寝かす」という言葉がありますが、一般的に紙は漉きたてのものよりも数年経ったものが良い、と言われています。
寝かせる期間は一概に言えませんが、10年寝かせるのが理想、という書家の方もいらっしゃいます。
作りたい作品のテイストやご自身の好みによりますので、いろいろと試してみてお好みの期間を見つけていただければ幸いです。
紙を寝かせるメリット
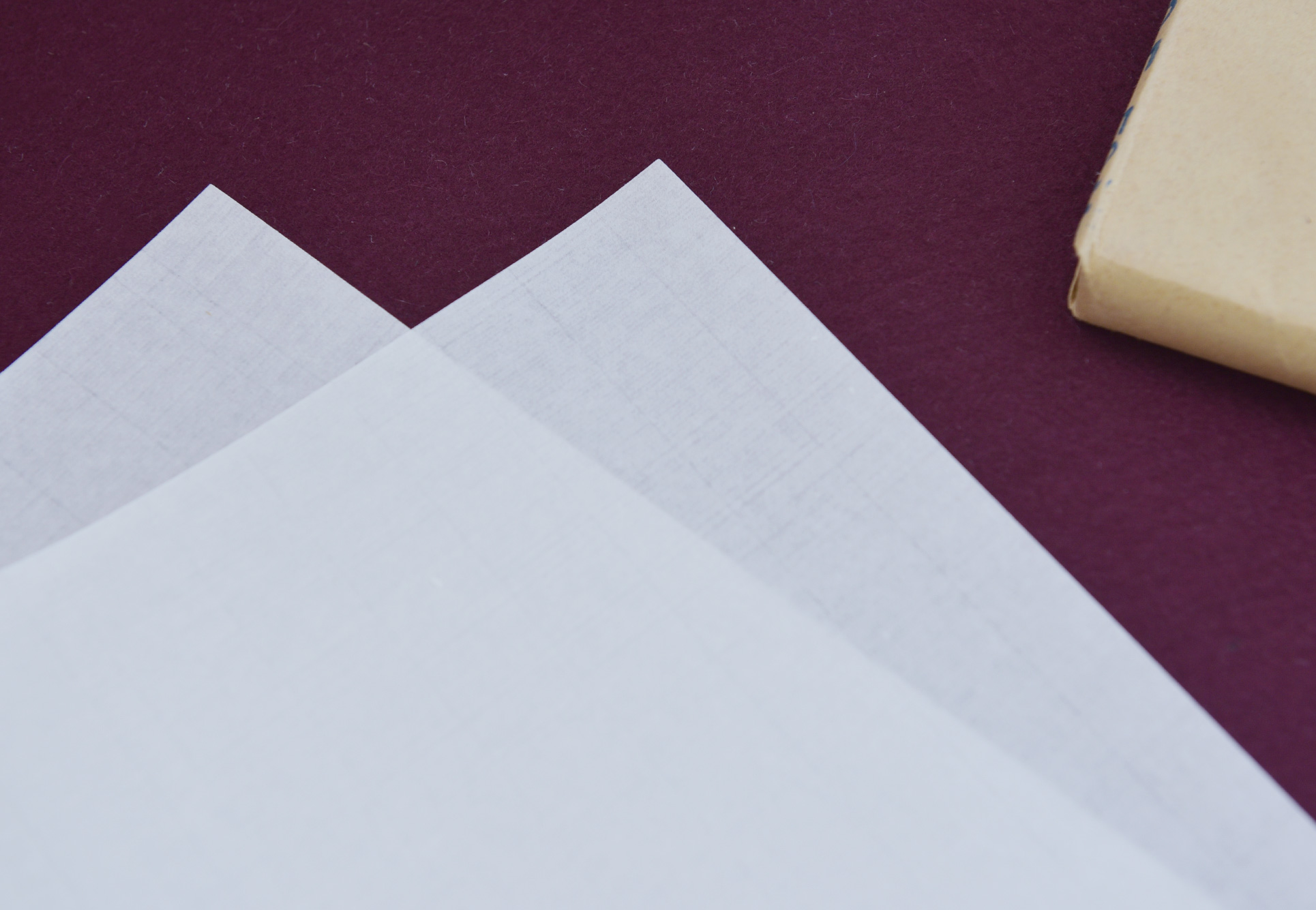
紙を寝かせることによって余分な水分が抜け、紙の繊維が締まり、
①墨が紙に十分に浸透するが、にじみが少なくなる
②墨色が美しくなる
③かすれが美しくなる
④筆の紙離れが良くなり、書きやすくなる
といった効果が得られます。
紙は湿気を吸い、湿気を吐き出し、それを繰り返すことによって、糊気と水分を飛ばしていきます。
その糊気や水分を飛ばして乾燥した状態の紙を『枯れた紙』といいます。
この『枯れた紙』は、筆あたりが良く墨色の発色の良いのはもちろん、にじみとかすれを美しく表現することができます。
紙を寝かせることによって、多少黄ばみやシミ(「星」と呼ばれる)が出ることもありますが、
正しい保存方法であれば、逆に重宝がられる事もありますのでご心配には及びません。
なお、にじみ止めや染料を使っている紙(料紙、加工紙、機械漉画仙紙 等)は、寝かせても意味がありません。
長期保存するとかたくなったり、折れやすくなったりすることがありますのでご注意ください。
紙も風邪を引く!?
一方で、十分に寝かせていても保存方法を間違えると、墨をのせたときに斑点のように白く浮き上がってしまうといった「紙が風邪をひく」という現象が起こります。
寝かせ方によって、漉きたての紙よりも質を低下させる事もありますので、紙の保存には十分な注意が必要です。
まとめ
作品づくりに欠かせない書道紙。保存方法に気を付けることで、作品の質もぐっと上がります。
正しい保存方法で紙を寝かせて、筆あたりの良さやかすれの美しさを味わってみてください。
また、近年は紙が製品化されてからお客様の手に渡るまでの期間が昔と比べて数カ月早まっており、紙の自然乾燥期間が短くなっております。
そのため、お客様のお手元に届く時点では昔のような乾燥期間を経ておらず、ニジミが治まりきらない状態に近いため、多くの紙に「ニジミ止め」が施されています。
このニジミ止め効果は、数カ月毎にニジミ止め効果が高まるため、昔のように紙を寝かせ過ぎると全く墨の入らない紙質に変化してしまう恐れがあるのが実情となっております。